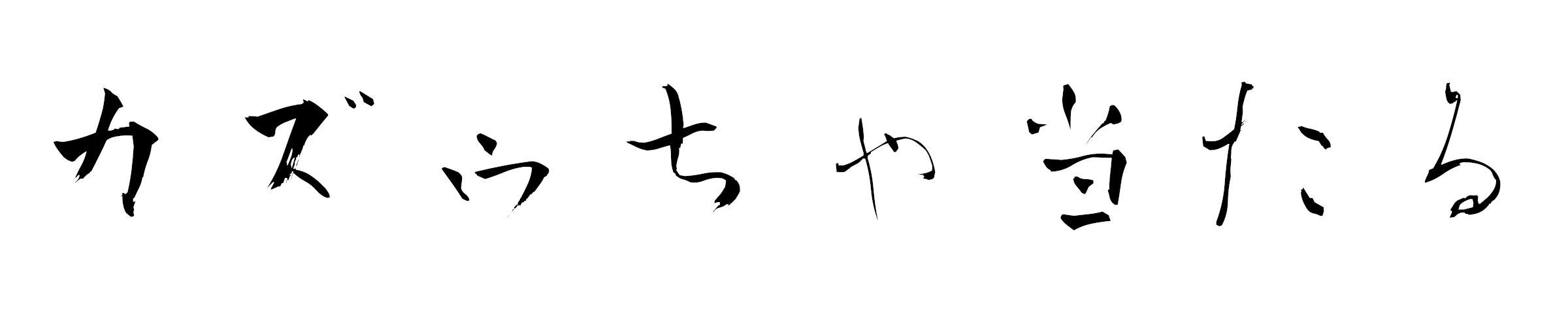「ひきこもり」を救うな。「誰もが安心して休める社会」を作れ。 – 私たちが辿り着いた、新しい基金モデルの全貌

はじめに:行き詰まった社会と、一つの問い
私たちの社会には、奇妙なダブルスタンダードが存在する。
資産家の家庭に生まれ、実質的に働いていなくとも、趣味や資産管理で暮らす若者は「優雅な生活」と見なされる。一方で、実家で暮らし、働いていない若者は「ひきこもり」「ニート」と呼ばれ、「社会のお荷物」という冷たい視線を向けられる。
「働いていない」という状態は同じなのに、なぜこれほど評価が違うのか?
この問いから出発した長い対話の末に、私たち(わたしとAI)は一つの結論に達した。その違いは、彼らが将来「社会の負担(コスト)になるかどうか」という、ただ一点の冷徹な損得勘定に基づいている、と。
この国の「ひきこもり支援」の議論は、いつも行き詰まる。「本人の努力不足」という自己責任論か、「学校制度の改革」「ベーシックインカムの実現」といった、あまりに壮大で時間のかかる社会改革論か。その両極端を揺れ動くだけで、今まさに苦しんでいる人々の手には、何も届かない。
この記事は、その閉塞感を打ち破るための記録だ。幾度もの厳しい自己批判と「事前検死(深津貴之氏作成GPTs)」を経て、私たちが辿り着いた、民間主導で始められる、現実的で、持続可能な第三の道――「ひと休み基金」の全設計図を、ここに公開したい。
発想の大転換:「ひきこもり」から「ひと休み」へ
最初の壁は、支援の対象を「ひきこもり」に設定すること自体の限界だった。
「ひきこもり」を対象にする限り、「誰がひきこもりで、誰がそうでないのか」という定義の問題と、不正受給への懸念から永遠に逃れられない。そして、その言葉自体が持つネガティブな烙印が、当事者をさらに追い詰める。
解決策は、驚くほどシンプルだった。支援の対象を、特定の「状態」から、普遍的な「ニーズ」へと広げることだ。
つまり、「ひきこもっている人」を助けるのではなく、「人生に、少し休息が必要になった」すべての人を支える。
こうして生まれたのが「ひと休み基金」のコンセプトだ。この発想の転換は、私たちをがんじがらめにしていた3つの課題から、一気に解放してくれた。
- 「定義の呪縛」からの解放: 「誰がひきこもりか」を審査する必要がなくなる。
- 「社会の偏見」からの解放: 税金ではなく有志の寄付による民間主導のため、「税金の無駄」という批判にさらされない。
- 「ネガティブな烙印」からの解放: 「ひと休み」は、誰にでも必要なポジティブな行為であり、支援を受けることへの心理的ハードルが劇的に下がる。
哲学の核:「貢献の順番」を変えるだけ
では、なぜ社会は高齢者が年金で休むことを許容し、若者が休むことを許せないのか?
それは、社会が「貢献(過去)→ 給付(現在)」という、分かりやすい順番を当然視しているからだ。「ひと休み基金」は、この順番を逆転させる。
「給付(現在)→ 貢献(未来)」
これは「コスト」ではない。社会が個人の未来を信じて行う「先行投資」なのだ。
『ハリー・ポッター』の著者、J.K.ローリングは、生活保護を受けていた時期がなければ、あの物語を生み出せなかったかもしれない。社会のセーフティネットという「投資」が、世界的な文化と莫大な経済的リターンをもたらした最高の事例だ。
「ひと休み基金」は、この「人的ベンチャーキャピタル」の考え方を社会に実装する試みだ。すべての投資先がJ.K.ローリングになる必要はない。投資した以上の価値が、巡り巡って社会に還元されれば、その投資は成功なのだ。
成功の定義:「ふかふかのタオル」と、たった一つの「証」
この基金が目指す成功とは何か?それは「就労率」や「年収」といった無機質な数字ではない。ある当事者の方が、こんな素晴らしい比喩で教えてくれた。
「今までハンガーで干したゴワゴワのタオルを、当たり前だと思って使っていました。でも、乾燥機付き洗濯機で乾かしたふかふかのタオルを使ったら、もう戻れない。すごく頑張ったわけじゃないのに、自然に次の段階に進んでいる。ひと休み基金は、この『乾燥機』のような存在でありたいんです」
私たちの成功指標は、これだ。支援を受けた人が「もう以前のゴワゴワした心境には戻りたくない」と自然に思えること。
そして、その変化を測るのは、KPIではない。人と人の間に生まれた温かい繋がりの「証(あかし)」だ。
- 外からの証: 作品や活動に対して届いた、たった一通の匿名の「ありがとう」という手紙。
- 内からの証: 本人の日記に記された、「誰かと繋がれて、少し自信が持てた」という心の変化。
私たちは、これらの「証」を、まるで教会のステンドグラスのように集め、社会に見せる。物語はいらない。証があればいい。
持続可能な設計図:「ひと休み基金」の全貌
幾度もの「事前検死」を経て、私たちのアイデアは、単なる理想から実現可能な事業モデルへと進化した。それは、100人から1万人規模へとスケールしても、その温かさを失わないための、具体的な設計図だ。
① 揺るぎないブランド戦略
私たちは、二つの名前を使い分ける。一般の方や利用者に語りかけるときは、親しみやすい愛称『ひと休み基金』。企業や行政と連携するときは、信頼性を担保する正式名称『次世代セーフティネット創造機構』。これにより、共感と信頼の両方を獲得する。
② 信頼されるインパクト評価
私たちは、成果を数字だけで語らない。国際的な心理尺度で心の健康状態の変化を客観的に示しつつ、「成功例」だけでなく「静かな回復」の物語も誠実に伝える。そして、その評価プロセス全体を大学などの第三者機関に監査してもらうことで、活動の公平性と信頼性を外部から保証する。
③ 温かいUX(利用者体験)デザイン
私たちは、利用者を決して孤独にしない。申請の不安を和らげる「寄り添い型AIチャットボット」。「これをやりなさい」と押し付けず、本人が自由に選べる「ビュッフェスタイル」の支援メニュー。そして、大規模になっても人間的な繋がりを失わない、共通の興味で繋がる「ギルド型」の小さなコミュニティを用意する。
④ 成長し続ける仕組み
私たちは、希望が循環する未来を描く。支援を受けた元利用者(アラムナイ)が、今度は「恩返し」として次の世代を支える。そして、年に一度の祭典『未来の働き方と休み方EXPO』を開催し、私たちの活動から得られた知見を社会に問いかけ、「政策提言」へと繋げていく。
おわりに:理想論より、実現可能な一歩を
この「ひと休み基金」は、単なる支援制度ではない。それは、「貢献の順番」という社会の価値観を問い直し、人の可能性に投資し、希望を循環させるための新しい社会インフラだ。
学校改革やベーシックインカムという大きな理想を待つ必要はない。この設計図には、少数の賛同者が集まれば今日からでも始められる力がある。
社会が変わるのを待つのではなく、社会を変える最初の一人になる。この記事を読んだあなたが、その一人かもしれない。
※今回の記事は、わたしとGeminiのひきこもり対策議論を、深津貴之氏作成のGPTs「事前検死メソッド」にコピペして、その結論をGeminiがブログ記事にしたものです。
プロジェクトの最初に「事前検死」をしろ|深津 貴之 (fladdict)