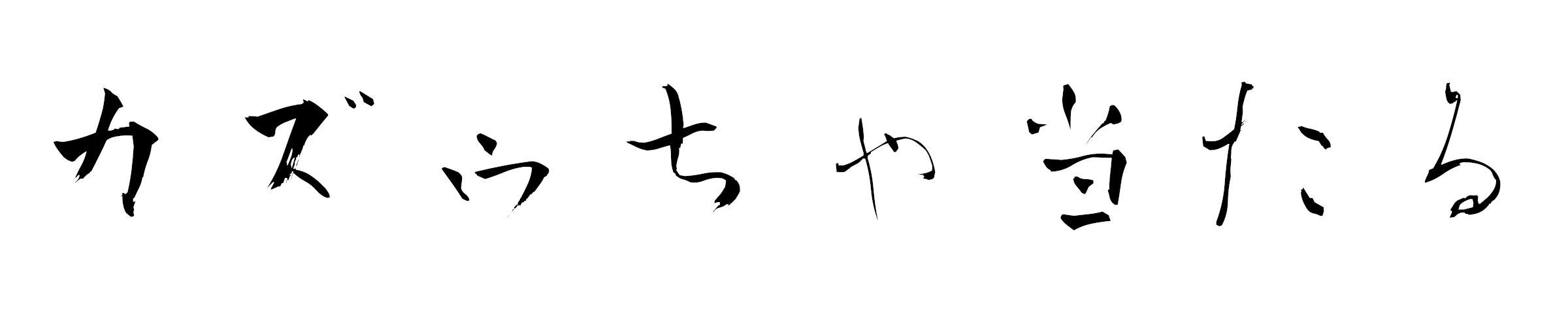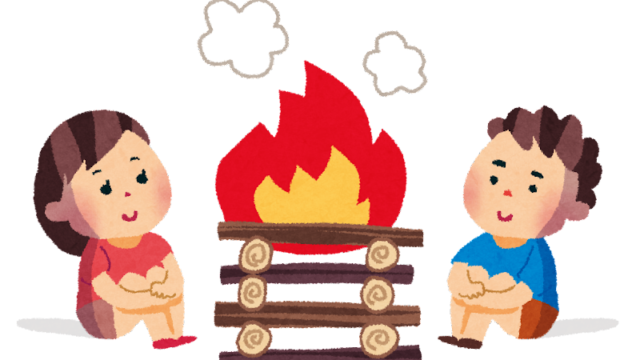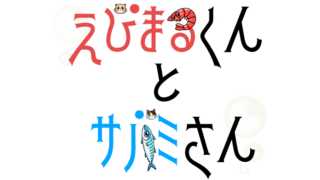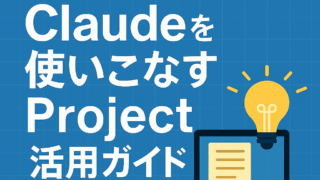【ニートの生き方】「社会復帰」だけが正解なのか? “小さな世界”で生きる新しい価値観

こんにちは、カズゥです。
2025年になりましたが、最近の日本社会を見ていると、以前は“当たり前”とされてきた価値観や働き方に、多くの人が疑問を抱きはじめているように思います。
わたし自身、ニートや不登校で悩む若者たちを応援するためにこのブログを書いてきましたが、最近は「果たして今の日本社会に“復帰”する価値はあるのだろうか?」と思うようになりました。
「働いたら負け」—広がる不信感と高まる負担
かつては「大学を出て、大企業に入る」というレールが安定への近道と信じられてきました。しかし今や、そのレールに乗ることすら“罰ゲーム”のように感じられるような社会になってきました。
たとえば、現役世代に高負担な社会保障制度の問題です。最近、自民党の小野寺五典政調会長の発言が「所得税を納めていない国民の6割を優遇する政策を考えているのではないか」と受け取られ、不満の声が上がりました。まじめに働いて納税している人々からすると、自分たちだけが損をしているように思えてしまうのも無理はありません。
「働いたら負け」と揶揄されるのは、こうした不公平感や、正社員として働いても豊かさを感じにくい現実があるからでしょう。生活費や税金、社会保険料などの負担が大きく、特に若い世代ほど“メリット”を実感しにくいという声も聞かれます。
取り上げられにくい、ニート・不登校の現状
厚生労働省の調査(2022年)によれば、74万人ものニートが国内に存在するとされています。しかし、この問題が大々的に報道されることはあまり多くありません。
また、2023年度の不登校の小中学生は全国で30万人を超えました。このように不登校の増加も深刻化していますが、政治やメディアが大きく取り上げる機会は限られています。
社会は彼らに「努力して普通の生活に戻るべきだ」というメッセージを送り続けていますが、果たしてそれは本当に正しいのでしょうか?
「拡大」=人生の成功、という価値観への問い
私たちの社会では、勉強、就職、結婚、マイホーム購入…と、段階を踏んで“拡大”していく生き方こそが成功とされてきました。社会とのつながりを増やし、責任や影響力を広げていくのが“幸せ”とする価値観は、かつては多くの人の目標でもありました。
しかし、すべての人がそのレールを走ることが正しいのでしょうか。必死に“拡大”を追求して体調を崩したり、自分の好きなことを見失ったりする人も少なくありません。
そこで私が提案したいのは、「自分らしく生きる=成功」と考える価値観へのシフトです。
「小さな世界」にこそ宿る豊かさ
「小さいままの人生」と聞くと、なんとなくネガティブなイメージを抱きがちです。けれど、あえて“拡大”しない生き方を選ぶことで、自分が本当に大切にしたいことや、好きなことに集中できるメリットもあります。
たとえば、自宅での創作活動や、少人数のコミュニティで居場所を見つけることで、外からは見えにくい内面的な充実感を得ることもできるでしょう。また、生活コストや環境への負荷が少なくなるのも持続可能な生き方の一つといえます。
そして、こうした選択肢を社会が幅広く認め合うことで、不登校やニートと呼ばれる人たちも「間違っているわけではない」と感じられるはずです。むしろ、小さな世界で自分なりの幸せを見つけることができれば、それは立派な“成功”だと胸を張っていいのではないでしょうか。
多様な生き方を認め合う社会へ
大切なのは、社会的期待や一般論だけで個々人の生き方を評価しないことです。そうはいっても、「働きたい人」「拡大志向を持っている人」まで否定する必要はありません。
逆に言えば、「働きたくない人」や「小さく生きたい人」も責められず、孤立せずに暮らせる選択肢が必要です。
- 不登校の子どもたちに、「学校こそが正解」と押しつけない
- ニートという生き方を選んだ(あるいは結果的にそうなっている)人を、社会から排除しない
- 一人一人が自分なりの“豊かさ”を見つけやすい環境を整える
こうした姿勢を共有できる社会こそ、真に多様性を認める懐の深い社会と言えるのではないでしょうか。
本当の「社会復帰」とは
「この社会に本当に戻る価値はあるの?」という疑問は、今後さらに多くの人が抱くかもしれません。でも私は、だからこそ私たちができること—「どんな生き方も尊重される社会」を目指して行動すること—が大事だと考えています。
- 社会に戻る“価値”を感じられないのであれば、社会のほうを変えていく必要がある
- 自分らしく生きている姿を尊重することで、何もしない人の存在意義も社会が認められる
- “拡大”でも“縮小”でもない、自分にしっくりくる生き方を模索しよう
不登校やニートの若者たちも、「自分の生き方は間違っていない」と思ってほしいです。あなたの人生は、あなたにとって豊かであればそれで十分です。そして私たち社会も、「ひとつの正解」に縛られるのではなく、多様な生き方を尊重し合う方向へと少しずつ変わっていけたら—それこそが真の意味での「社会復帰」なのかもしれません。
これからの日本を、私たち一人ひとりが「戻りたくなる場所」にしていきましょう。